自己理解と他者理解が交わる場所
昨日ふと、「自己理解と他者理解」のことを1人で考えていました。
1人でいるよりも他者と交わる方が自分ってどんな性質性格なのかが分かる、という、心理学や自己啓発界隈では有名な考え方のやーつです。
当たり前ですが顔や体は目に見えるので他者と比較がしやすく、自分ってどういうタイプの器量かはあまりズレなく認識できると思います。
対して性格には形がないので、他者と言葉を交わす中で「そう考えるんだ」「そう判断するんだ」ってなって形が見えてくるわけです。
これがですね、自分が思ってた以上にずれてるな、というのを最近殊に感じるんです。
自分って◯◯なんだ…!と感激orショックを受けることがしばしば。◯◯には長所、短所、長所をひっくり返した短所などが当てはまる感じです。
たとえば、自分では「普通」と思っていた習慣が、誰かにとっては「そんなめんどくさいこと毎日してるの?」と驚かれたり。
逆に、相手の身軽な行動に対して「えっ、そんな風に肩の力抜いてもいいんや…!」となったり。
言葉を交わす中で、相手の思考の輪郭が見えると同時に、自分の考えのクセや価値観も浮き彫りになっていく。
この体験を繰り返すことで、少しずつ「自分はこういう性質なんだな」という理解が育っていくんだと思います。
私の場合、専業主婦歴10年という環境もあって、社会との関わりがずっと小さな世界に留まっていたことも関係していると思います。
その間、自分の“社会での立ち位置”を見つける機会はなかなかありませんでした。ママ友とか社宅のお母様方とかね。すごく小さな、共通項子どもっていう単位の世界。それが悪いわけではないけど視野の広がりにはある程度の限界はありますよね。
そこから子育てが少し落ち着いて、ハンドメイド作家としての活動をちょこっと始めたり、税理士事務所での仕事を始めたりして、気づけば社会復帰して3年。
これはもう例えるなら、金魚鉢から太平洋へと泳ぎ出したような感覚。いや太平洋は言いすぎかな。瀬戸内海ぐらい。
日々、本当にいろんな方と出会って、心から思うのは「人って、ほんまにいろんな人がいるなぁ」ということです(語彙力…!)。
「自分の得意は誰かの不得意だから、自分の何気ない行動や言動が人の役に立てる」
この言葉は私にとって、とても救いになる考え方です。
「誰かを助けたい」「社会の役に立ちたい」っていう思いはあるけれど、じゃあ何ができるのかと問われると、すぐに答えられない。
でも、まずは“自分の得意”を見つめてみることが、最初の一歩なのかなって。
昨日、そんな話を友人と玄関先で立ち話していて、「やっぱり私は、これが好き、これが得意、と小さな旗を立てることが大事なんやな」と改めて思いました。
誰かの役に立てるかどうかは分からないけれど、せめて自分には「これは大切にしている」というものを持っていたい。
静かに、自分の旗を立てておく。
その旗が誰かの目に留まり、「それ、いいね」と言ってもらえる日を信じて。
それでは聞いてください、
Mr.Childrenで「名もなき詩」
(知らぬ間〜に築いてた〜自分らしさの檻の中で〜)

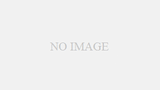
コメント